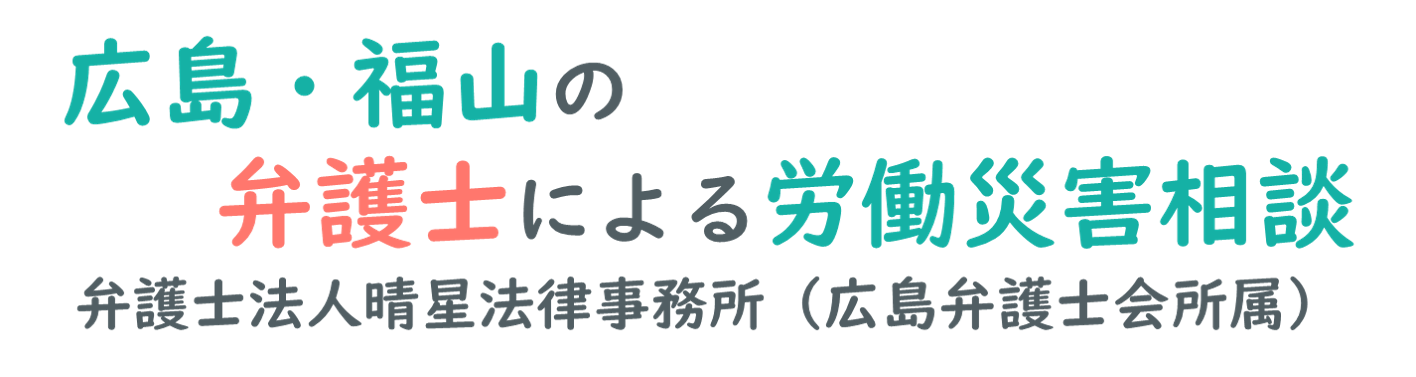目次
墜落・転落による死亡事故は、業務中の事故に占める割合が高く、重症化しやすいケースです。労働災害による死亡者数は年々減少傾向にあるものの、例年、死亡者数の25~30%前後を墜落・転落事故が占めています。
墜落・転落事故は、休業4日以上の受傷者数においても高い割合を占める類型です。墜落・転落事故に遭うと、お亡くなりになることも珍しくありませんし、重い後遺障害が残存することも多いです。
墜落・転落事故が発生する原因には、手すり、歩み板、命綱、落下防止の網等の安全を確保する設備が設けられていなかったこと、墜落・転落を防止するための安全教育がなされていなかったこと、足を踏み外すなどの不注意等様々なものがあります。
墜落・転落事故が特に多いのは「建設業」
墜落・転落事故は、建設業における労働災害の大部分を占める事故類型となっています。
墜落・転落による労働災害を防止するための対策としては、次の点が挙げられています。
①墜落・転落災害防止に係る労働安全衛生規則の遵守徹底を図る。また、令和5年3月に足場点検の確実な実施のための措置、一側足場の使用範囲の明確化を内容とする労働安全衛生規則の改正が行われており、その順守の徹底を図る。
②フルハーネス型墜落制止用器具の適切な使用の徹底を図る。
③はしごや脚立の安全な使用の徹底を図る。
このように、建設業においては、墜落・転落事故による労働災害が多く発生しています。
業務中に墜落・転落事故に遭ったら労災申請をする
業務中に、墜落・転落事故に遭って怪我をされた場合、まずは労災申請から始めましょう。
労災申請は、基本的には、労働者の所属事業場の所在地を管轄する労働基準監督署に対して行います。労働者が労働災害によって負傷したことが認定されると、労災保険給付を受給することができます。
主な労災保険給付は以下のとおりです。
療養(補償)給付
労働災害によって怪我等をした被災労働者の治療費、治療関係費が支給されます。療養(補償)給付には、労災病院等の指定医療機関等で無料で治療や薬剤の支給を受けることができる「療養の給付」と、指定医療機関等以外で治療等を受けた場合にその費用が支給される「療養の費用の給付」があります。
「療養の給付」と「療養の費用の給付」では、申請する際の様式が異なり、「療養の給付」の場合は様式第5号(通勤災害の場合は様式第16号の3)を、「療養の費用の給付」の場合は様式第7号(通勤災害の場合は様式第16号の5)を提出します。
休業(補償)給付
労働災害による負傷や疾病による療養のために労働することができず、そのために賃金を受けていないときには、休業(補償)給付・休業特別支給金が支給されます。休業の初日から第3日目までは待期期間となっているため、第4日目から支給されます。
休業(補償)給付の支給額は、給付基礎日額の60%×休業日数で、休業特別支給金の支給額は、給付基礎日額の20%×休業日数です。
休業(補償)給付の申請は様式第8号(通勤災害の場合は様式第16号の6)を提出します。
障害(補償)給付
労働災害による負傷や疾病が治ったときに、一定の障害が残った場合に支給されます。
後遺障害等級には第1級から第14級まであり、等級によって給付金額も異なります。第
1級から第7級までは年金が、第8級から第14級までは一時金が支給されます。
障害(補償)給付の申請は様式第10号(通勤災害の場合は様式第16号の7)を提出します。
遺族(補償)等給付、葬祭料(葬祭給付)
遺族(補償)等給付は、労働災害が原因でお亡くなりになった労働者の遺族に支給されます。
葬祭料(葬祭給付)は、上記労働者の埋葬を行った遺族等に支給されます。
遺族(補償)等給付には、遺族(補償)等年金と遺族(補償)等一時金があり、被災労働者の収入によって生計を維持していた妻等の遺族がいる場合には遺族(補償)等年金が、遺族(補償)等年金を受け取る遺族がいない場合等には遺族(補償)一時金が支給されます。
遺族(補償)等年金の申請は様式第12号(通勤災害の場合は様式第16号の8)を、遺族(補償)一時金の申請は様式第15号(通勤災害の場合は様式第16号の9)を提出し、埋葬料(埋葬給付)の申請は様式第16号(通勤災害の場合は様式第16号の10)を提出します。
会社や元請に対する損害賠償請求が可能なことも
墜落・転落事故では、重篤な後遺障害が残存したり、お亡くなりになったりすることも少なくありません。一方、労災保険から療養(補償)給付や休業(補償)給付等は支給されるものの、慰謝料などは労災保険から支払われません。そのため、墜落・転落事故に遭われたときには、会社や元請に対する損害賠償請求も検討するべきです。
使用者である会社には、労働者がその生命・身体の安全を確保しつつ労働することができるように必要な配慮をする義務(安全配慮義務)が定められており(労働契約法5条)、会社が同義務に違反して墜落・転落事故が発生した場合には、会社に対して損害賠償を請求することができます。また、会社に安全配慮義務違反が認められる場合、通常は不法行為責任(民法709条)にも該当します。
また、会社の従業員からその事業の執行について損害を加えたときは、当該従業員のみならず、使用者である会社に対しても損害賠償を請求することができます(使用者責任・民法715条)。
なお、安全配慮義務は使用者ではない元請に対しても認められることがあります。
墜落・転落事故の場合、墜落防止措置を講じることが可能であったにもかかわらず、歩み板、命綱、落下防止の網といった安全を確保する設備が全く備えられていなかった等、会社に安全配慮義務違反が認められる可能性があるケースも多いです。
また、業務中、他の従業員の行為が原因で墜落・転落事故が発生した場合には、使用者責任(民法715条)として、会社に対して損害賠償が請求できる可能性もあります。
会社や元請に対して損害賠償を請求する流れ
労災が認定されると、労働局に対する保有個人情報の開示請求などにより、診療費請求内訳書(レセプト)や調査復命書等の資料を収集します。なお、保有個人情報の開示請求は労災が認定されなかった場合にも行うことができます。
収集した資料をもとに、会社や元請に責任があり、損害賠償請求が可能かどうか検討します。損害賠償請求が認められる可能性がある場合、損害額を計算して、会社や元請に対して、損害賠償を請求します。
墜落・転落事故における会社や元請の具体的な責任の一例は次のとおりです。
- 歩み板、命綱、落下防止の網等の墜落防止設備が備えられていなかった
- 墜落・転落防止のための安全教育が行われていなかった
- 作業環境の点検が行われていなかった
- 危険な場所への立ち入りを禁止していなかった
会社や元請と交渉で合意ができれば示談が成立します。合意ができなければ労働審判や訴訟といった裁判所を利用する手続によって、会社や元請に対して損害賠償を請求します。
労働審判や訴訟といった裁判手続に移行した時点で、弁護士に依頼をするというイメージを持たれている方も多いかと思います。
しかし、労働災害に遭うこと自体初めての方が多く、ご自身ではどのように資料の収集や交渉を進めればよいのか分からず、途中で手続きをやめてしまう方もいます。
また、会社側からも、被災労働者の不注意が原因であり、会社側に過失がないとか、元請から雇用関係にないので責任はないといった主張をされることも多く、ご自身で対応するのは負担がかかります。
弁護士にお任せいただくと、弁護士が代わって会社と交渉し、適切な主張・反論を行います。
業務中に墜落・転落事故に遭われてお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください
墜落・転落事故に遭われたら、まずは労災申請から始めることが重要です。
労災申請や会社に対する損害賠償請求には専門的な知識が必要になることもあります。
弁護士にご相談いただければ、個別の事情を踏まえて、労災申請の流れや会社等に対する損害賠償請求について具体的にアドバイスをもらうことができます。
業務中に墜落・転落事故に遭われてお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。