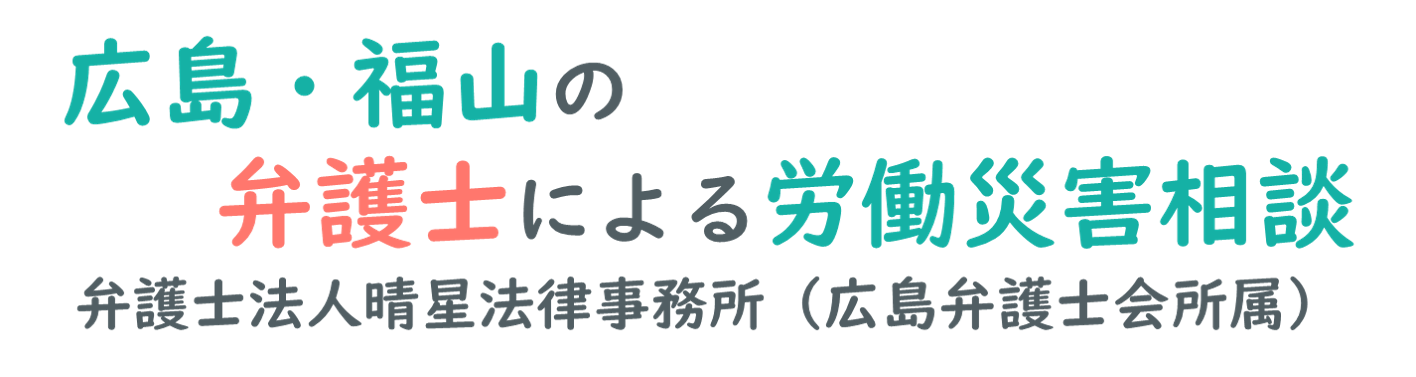休業補償給付とは
休業補償給付は、労働災害(労災)によって働けなくなった労働者が、一定の生活保障を受けるための制度です。
労災保険に基づき、休業中に得られなかった賃金の一部を補償する目的で支給されます。
この制度は、労災事故後の治療やリハビリに専念できる環境を整えるために重要な役割を果たしています。
ただし、休業補償給付が全額の補償をカバーするわけではないため、その詳細を理解することが必要です。
休業補償給付を受けるための3つの要件とは
休業補償給付を受けるには、以下の3つの要件を満たしている必要があります。
業務上の事由または通勤による死傷や疾病であること
労災保険が適用されるのは、業務上の事由または通勤による死傷や疾病です。
「業務上の事由による死傷」に当たるか否かは、「労働者が事業主の支配ないし管理課にあるか(業務遂行性)」と「労働者が労働契約に基づき事業主の支配下にあることに伴う危険が現実化したと経験則上認められか(業務起因性)」により判断します。
例えば、工場作業中の事故やオフィスでの転倒事故などであれば、業務遂行性・業務起因性とも認められやすいです。
ただし、事業場外での参加が任意であった忘年会や(業務遂行性なし)、喧嘩の結果である場合(業務起因性なし)などには適用対象外とされる可能性が高いです。
また、「業務上の事由による疾病」については、対象となる疾病が、労働基準法施行規則別表1の2に列挙されています。
「通勤による死傷や疾病」における「通勤」については、労働者災害補償保険法7条2項に要件が列挙されています。
労働することができないこと
診断書は必要ありませんが、請求書(様式第8号ないし様式第16号の6)の「診療担当者の証明」欄について、通院した病院又は診療所の診療担当者(医師・歯科医師・柔道整復師等)に必要事項を記載してもらうことにより、「働くことができない」と証明してもらうことが必要です。
賃金を受けていないこと
休業補償給付は、賃金が支給されていない場合に適用されます。例えば、有給休暇を利用して給与が支払われている期間や、企業から特別手当が出ている場合は対象外となることがあります。
休業補償給付の補償内容とポイント
賃金の全額が補償されるわけではない
休業補償給付で支給される金額は、賃金の全額ではなく、通常「給付基礎日額」の80%相当額です。これは、60%が休業補償給付として、20%が休業特別支給金として支払われます。
実際にどれだけもらえるのか(計算例)
具体的な支給額を計算するには、給付基礎日額を基準とします。
給付基礎日額は,労働者の平均賃金に相当する金額のことをいいます。
平均賃金は、負傷の原因となる事故が発生した日または、医師の診断により疾病の発生が確定した日の直近3ヶ月間に、被災労働者に対して支払われた賃金の総額(ボーナスや臨時に支払われる賃金を除く)を、その期間の暦日数で割った1日当たりの賃金額により確定します。
計算式
支給額=給付基礎日額 × 80% × 休業日数
例えば、直近3ヶ月に支払われた賃金が,いずれも30万円の場合、給付基礎日額は以下のように計算されます。
給付基礎日額 = (30万円+30万円+30万円) ÷ 90日 = 1万円
支給額 = 1万円 × 80% = 8000円/日
これを休業日数に掛け合わせた金額が支給額となります。
休業補償給付の対象となる期間
休業補償給付の対象となるのは、休業4日目以降です。
事故発生日から3日間は「待機期間」とされ、この間の補償は労災保険ではなく、通常は事業主が労働基準法に基づく対応(1日につき平均賃金の60%の休業補償)をすることになります。
休業補償を受け取るための手続きについて
必要書類を労働基準監督署に提出する
休業補償給付を申請する際には、「休業補償給付・複数事業労働者休業給付支給請求書」(様式第8号)または「休業給付支給請求書」(様式第16号の6)を所轄の労働基準監督署長に提出する必要があります。
なお、休業が長期にわたる場合には、1ヶ月ごとの請求を行うのが一般的です。
休業補償を受け取るまでの時間
手続きが完了してから支給されるまでには、通常1か月程度かかります。
ただし、申請書類の不備や追加資料の要求がある場合、さらに時間がかかる可能性があります。
休業補償に時効はあるのか
休業補償給付の申請には時効があり、労災が発生した日から2年間です。
この期間を過ぎると申請権が消滅してしまうため、早めに手続きを行うことが重要です。
休業補償では十分ではない場合も
賃金全額の補償がされないことの課題
休業補償給付では平均賃金の80%しか支給されません。
また、精神的苦痛や将来取得することが見込まれた利益に対する補償は含まれていません。
これらの損害については、会社に対する民法上の損害賠償請求によらなければなりません。
このような制度となっているのは、労災補償制度が、労働災害による損害のうちの一部を簡易迅速に補償することで労働者の保護を図ることを目的として出発していることに起因しています。
会社への損害賠償によるカバー
労災が会社の安全配慮義務違反に起因している場合、損害賠償請求を行うことで不足分を補うことができます。
例えば、機械の整備不良や安全教育の不足、過重労働などが該当します。
損害賠償請求では、休業補償でカバーされない精神的苦痛や逸失利益も含めて請求可能です。
弁護士に相談を
労災に関連する手続きは、複雑で時間がかかることが多いです。
また、会社との交渉や損害賠償請求には専門的な知識が必要です。
弁護士に相談することで、スムーズな手続きや適切な補償を受け取るためのサポートを受けられます。
弁護士への相談のメリット
・書類作成や手続きのサポート
・会社との交渉や損害賠償請求の代理
・労災保険給付の増額請求の可能性を検討
労災に遭った方が安心して生活を取り戻すためには、専門家の助けを借りることが重要です。
まずはお気軽にご相談ください。