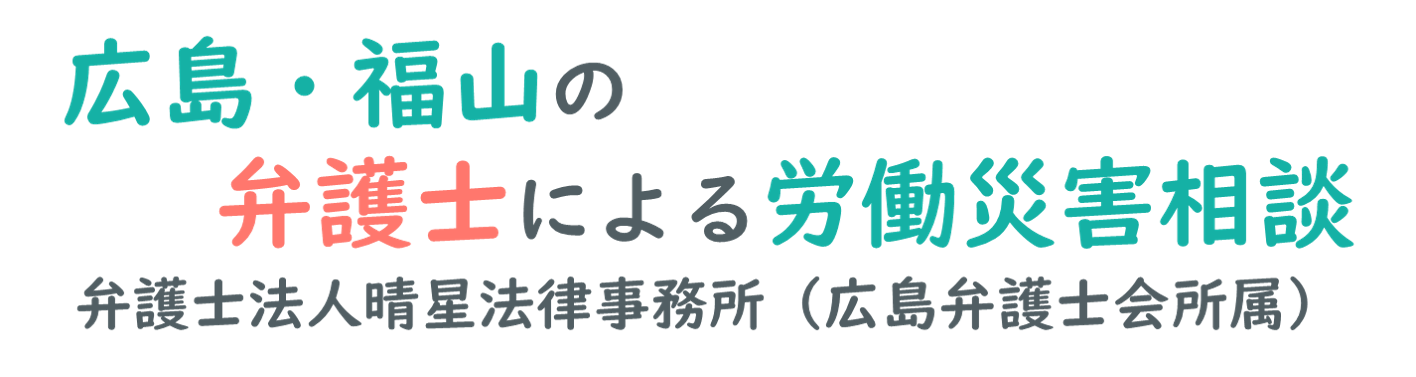労働災害とは
法律上の定義
労働災害について、労働災害の防止のための危害防止基準の確立を目的の一つとする労働安全衛生法は、「労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行為その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡すること」と定義しています(労安衛法2条1号)。
要するに労働災害とは、労働者が労務に従事していることによって被った死亡、負傷、疾病をいいます。
なお、労災補償の大部分の機能を担っている労働者災害補償保険法は、「労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡」を「業務災害」と定義しており(労災保険法7条1項1号)、労安衛法における「労働災害」と労災保険法における「業務災害」は同一の概念を示しています。
具体例
労安衛法2条1号には、労働災害をもたらす要因として「労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等」および「作業行為」が規定されていますが、これは労働災害をもたらす要因を例示的に列挙しているだけに過ぎません。
労働災害をもたらす要因は多岐にわたり、また、時間的場所的に識別できる出来事(事故)による負傷、疾病、死亡(一般的にイメージされる労働災害)のみならず、そのような出来事を識別出来ない(非災害性の)負傷、疾病、死亡も「労働災害」には含まれます。
非災害性の例としては、非災害性腰痛に代表されるように、約20㎏以上の重量物または重量の異なる物品を繰り返し中腰の姿勢で取り扱う港湾荷役や、長時間立ち上がることが出来ず、同一の姿勢を持続して行う長距離トラックの運送業務などが、これに当たります。
労災補償制度における労働災害(業務災害)に関する諸規定
制度の概要
労災補償の主要立法である、労働者災害補償保険法は、①業務上の事由、または通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、②あわせて、それらの負傷、疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的としています(法1条)。
①の目的を遂行するものが「保険給付」であり、②の目的を遂行するものを「社会復帰推進等事業」といいます。
「保険給付」は「業務災害に関する保険給付」「通勤災害に関する保険給付」「二次健康診断等給付」の三本立てとなっています(法7条1項)。
また、「社会復帰促進等事業」としては、①被災労働者の円滑な社会復帰の促進のための事業(養護施設、リハビリテーション施設の設置、運営など)、②被災労働者およびその遺族の援護のための事業、③労働者の安全および衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保、賃金の支払の確保のための事業の三事業が行われています。
業務災害
「業務災害」とは、「労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡」をいいます。(労災保険法7条1項1号)。
・「労働者」とは
ここでいう「労働者」とは、労基法上の「労働者」(労基法9条)と一致した概念です。なぜなら、労災保険制度は、労基法上の労災補償制度を基礎として構築されているからです。そして、労基法上の「労働者」とは、「職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者」をいいます。
・「業務上」とは
ア 概要
ここでいう「業務上」と言えるためには、当該労働者の業務と負傷等の結果との間に、当該業務に内在または随伴する危険が現実化したと認められるような相当因果関係が肯定される必要があります。
また、この危険性判断に当たっては、使用者の個別的な補償責任の枠を超えて、事業主に共同で負担させるのが相当であるような労働者の労務遂行に定型的に伴う危険も考慮されると考えられます。
実際、労働者の遺族が行った遺族補償給付等の支給請求に対する労働基準監督署長の不支給決定に対する取消訴訟を求めた事案において、「A’は、A’が甲社を退職した後乙社に就職するまでの約3か月間は全く仕事に就いていないから、この間にA’の脳動脈瘤に影響を及ぼし得る労働実態はないといえる。また、A’が乙社に就職してから死亡するまでの間の乙社におけるA’の労働時間(時間外労働を含む。)、業務内容等の就労状況についても、その内容及び…医学的知見に照らすと、A’の脳動脈瘤に明らかに影響を及ぼす程度の過重なものであったとは認められない。」として、使用者である当該企業における業務に加重負荷は認められないとしつつ、「A’が甲社で従事した業務は、量的にも質的にも著しく過重なものということができるのに対し、甲社以外の就労先における業務は過重なものではなく、A’には、本件疾病の発症について、業務以外の確たる危険因子は認められない。そうすると、A’の脳動脈瘤は、甲社退職時点において既にいつ破裂してもおかしくない状態にまで増悪していたと推認されるものであり、その増悪は、先に説示した甲社における過重な業務により、その自然経過を超えて生じたものと認めるのが相当である。」として、転職前の会社で1年数ヶ月にわたる長時間労働につき、業務起因性を認め、遺族補償給付等の不支給決定処分を取り消しており、上記のような考え方が窺われるところです(東京地方裁判所平成23年4月18日判決)。
このような考え方は、労災保険制度が、使用者の労基法上の労災補償責任を事業主が集団的に共同で補填する制度であるという理解が根底にあると思われます。
なお、「業務上」といえるがという基準は、労働者が業務との関連で発生した事故によって負傷、死亡した場合と業務との関連で疾病に罹患した場合とで異なります。
イ 事故による負傷、死亡の業務性判断
労働者の負傷、死亡事故が生じた場合、その事故が「業務上」生じたか否かは、「業務遂行性」の有無を判断し、そのうえで「業務起因性」を判断して決するものとされています。
a 業務遂行性
「業務遂行性」とは、労働者が事業主の支配ないし管理下にある状態をいいます。
したがって具体的な業務を遂行している場合のみを指す言葉ではありません。
そのため、①事業場内で作業に従事中(作業に通常伴う用便、飲水などの中断を含む)の場合はもとより、②事業場内での休憩中や、始業前・終業後の事業場内での行動の際の災害や③事業場外で労働している時や出張中の災害でも業務遂行性が認められます。
このため、業務遂行性が認められない場面は、通勤途中および事業場外での任意的な従業員親睦活動や純然たる私的行動(生活)中の場合に限定されます
裁判例においても、業社外の忘年会への参加について業務遂行性が争われた事案においては、「労働者が事業主(使用者)主催の懇親会等の社外行事に参加することは、通常労働契約の内容となっていないから、右社外行事を行うことが事業運営上緊要なものと客観的に認められ、かつ労働者に対しこれへの参加が強制されているときに限り、労働者の右社外行事への参加が業務行為になると解するのが相当である。」「本件会合は、足羽道路企業株式会社が経費の全額を負担しているが、従業員の慰安と親睦を目的とするものであつて社会一般に通常行われている忘年会と変りはないから、本件忘年会を行うことが右会社の事業運営上緊要なものとは認められず、また右会社役員が従業員に対し、特に都合が悪い場合は格別、できるだけ参加するようにと勧め、参加者を当日出勤扱いにする旨伝えたことは認められるものの控訴人に対し本件忘年会に参加することを強制した事実は認められない。したがって控訴人が本件忘年会に参加したことを業務行為と解することはでき」ないとして、業務遂行性を否定しています(名古屋高裁金沢支部判決昭和58年9月21日)。
b 業務起因性
業務起因性とは、「業務又は業務行為を含めて「労働者が労働契約に基づき事業主の支配下にあること」に伴う危険が現実化したものと経験則上認められること」をいいます。
事業場内で作業に従事中の場合(上記①)であれば、原則として業務起因性が認められます。
ただし、自然現象(地震や雷)、外部の力(部外者が刃物を持って飛び込んできた場合等)、本人の私的逸脱行為(仕事上のことから争いとなり死亡した事案において、本人の挑発行為による喧嘩が災害の直接原因である事案(最高裁判所昭和49年9月2日)等)、規律違反行為(酒に酔って作業など)などによる場合、業務起因性は認められません。
もっとも、自然現象や外部の力について、当該職場に定型的に伴う危険(隣の工場の爆発など)であれば、業務起因性が認められます。
実際、阪神淡路大震災や東日本大震災においても、地震に際し、災害を被りやすい業務上の事情がある人の多くは、「業務上」という認定を受けています。
業場内での休憩中や、始業前・終業後の事業場内での行動の際の災害(上記②)の場合、業務との関連性がある場合や、事業場施設の不備・欠陥によるものでなければ、業務起因性が認められません。
事業場外で労働している時や出張中の災害の場合(上記③)、業務遂行性は広く認められます。
ただし、積極的な私的行動による災害であれば業務起因性は認められません。
ウ 業務上の疾病
業務上の疾病については、労基則35条が別表1の2として規定しています。
列挙すれば以下のとおりです。
| a 業務上の負傷に起因する疾病(災害性腰痛など) |
| b 物理的因子による一定の疾病(暑熱な場所での業務中の熱中症など) |
| c 身体に過度の負担のかかる作業態様に起因する一定の疾病(非災害性腰痛など) |
| d 化学物質等による一定の疾病(石綿にさらされる業務によるびまん性胸膜肥厚など) |
| e 粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症またはじん肺合併症 |
| f 細菌、ウィルス等の病原体による一定の疾病(病原体を取り扱う看護師等の伝染症疾患など) |
| g がん原性物質・因子またはがん原性工程における業務による一定の疾病 |
| h 過重負荷による脳、心臓疾患 |
| i 心理的負担による精神障害 |
| j 厚生労働大臣の指定する疾病 |
| k その他業務に起因することが明らかな疾病 |
通勤災害
通勤災害とは、「労働者の通勤による負傷、疾病、障害または死亡」をいいます(労災保7条1項2号)。
・「通勤」とは
労働者が就業に関し、以下の①から③のいずれかに該当する移動を、合理的な経路および方法により行い、業務の性質を有さないものを言います(労災保7条2項)。
ただし、これらの移動において経路を逸脱し、またはこれらの移動を中断した場合は、逸脱・中断の間およびその後の移動は「通勤」とはみなされません。
もっとも、これらの逸脱・中断が日常生活上必要な行為(日用品の購入、職業能力の開発向上のための受講、選挙権の行使、病院での診療、要介護状態にある配偶者、子、父母など一定の近親者の介護)であって最小限度のものである場合は逸脱・中断の間を除き、「通勤」に該当します(労災保7条3項、労災保則8条)。
① 住居と就業の場所との往復
② 就業の場所から他の就業の場所への移動
③ ①の往復に先行または後続する住居間の移動(単身赴任先と帰省先住居との移動を指します)
・「通勤による」とは
経験則上通勤と相当因果関係にあること、すなわち通勤に通常伴う危険が具体化したとみなされることを言います。
通勤途中の交通事故などが典型例です。
・「就業に関し」とは
業務に就くため、または業務を終えるため」という意味であり、移動行為と業務との密接な関連性を要求する趣旨である。
労働者が組合活動等のため、居残った後の帰路でも、社会通念上、就業と帰宅との直接の関連性を失わせるほど長時間経過後に帰路につく場合でない限り「就業に関し」といえます。
・「住居」とは
労働者の就業の拠点となる居住場所をいいます。
単身赴任者が、週末などに反復継続して自宅に帰宅する場合、赴任先の住居と帰宅する住居の双方が「住居」となります。
・「就業の場所」とは
業務を開始し、または終了する場所を言います。
本来の業務を行う場所以外にも、物品を得意先に届けて、そこから直接帰宅する場合は、物品の届け先が「就業の場所」に当たります。
・「合理的な経路及び方法」とは
一般に労働者が用いるものと認められる経路および手段をいい、通常用いている経路・手段ではなく、合理的な代替経路・手段も含まれます。
まとめ
以上のように、労働災害に該当するか否かの要件は複雑なものとなっており、これらをたてに、会社側が、労災ではないと主張してくる場合もあります。
ご自身の受傷が労働災害に当たるのか判断が難しいという方や、会社側が労働災害ではないと主張してきて困っているという方につきましては、お早めに、労災問題に精通した弁護士にご相談いただければと思います。