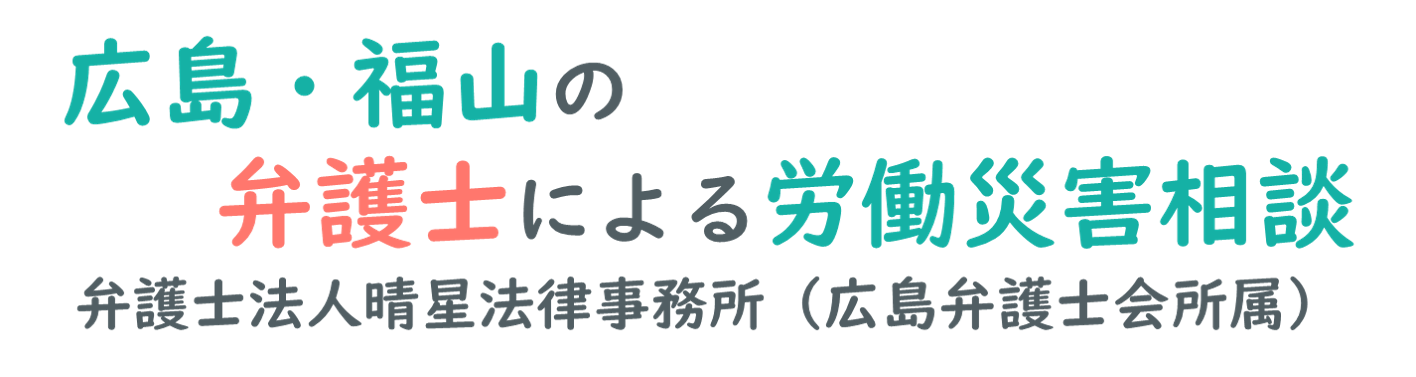プレス機とは/どのような事故が起こるか
工場などで金属やプラスチックなどの素材を「金型(型)に当てて圧力をかける」ことで成型・加工を行う機械を「プレス機」と言います。たとえば車の部品、パソコンの筐体、金属板の成形など、さまざまな用途で使われています。
このプレス機を使った作業では、以下のような事故が典型的です。
・金型によって手や指、腕を「挟まれて」「切断」された。
・加工した部材や金型の破片が飛んできて負傷。
・安全装置が機能せず、予期せぬ動作が起こることにより発生する重大事故。
なぜプレス機作業で労災が起きやすいのか
プレス機作業が労災リスクの高い作業である理由には次のようなものがあります。
・強大な圧力・高速での繰り返し動作を伴うため、少しの油断・ずれでも重大事故につながる。
・機械の構造上、「挟まれ・巻き込まれ」「切断」のリスクが高い。実際、製造業における死傷型別では「挟まれ・巻き込まれ」が多く報告されています。
・安全装置や点検・教育が適切に実施されていない事例が多く、安全配慮義務(会社側の義務)違反が認められるケースがあります。
事例
ある金属加工工場で、200トンクランク式のプレス機を用いてステンレス板の端部曲げ加工をしていた作業員Aが、金型交換の際に「安全ブロックを置き、加工品を落とす」方法で作業を続けていました。ところがこの安全ブロックが弾き飛ばされ、正面にいたAが激突を受けて死亡しました。調査では、10台のプレス機を使用しているにもかかわらず「プレス機械作業主任者を選任していなかった」「安全衛生教育が十分に行われていなかった」などの原因が指摘されました。
このように、「機械そのものの危険性」「安全体制の不備」「教育・監督の不備」が重なると重大事故に至ることがあります。
プレス機における労災の対処方
事故直後にすべきこと
プレス機で事故が起きてしまったら、次のように対処しましょう。
1.怪我をした場合、まずは 応急処置・医療機関を受診します。
救急対応を優先することはいうまでもありません。
2.事故があったこと・発生状況を 記録・保存 する。
例えば、「どの機械で」「何をしていた時に」「どういう金型・作業状態だったか」「安全装置は?」などをメモ・写真に残しておくと、後で役に立ちます。
3.会社・作業現場責任者に 事故報告 をする。
そして、会社が対応を避けている・事実を隠そうとしていると感じたら、労働基準監督署へ相談・報告を検討してください。
4.会社側と協力して、 労災申請(次章で詳述) に向けた準備を進める。
会社が労災申請を認めない場合や対応が遅い場合には、お早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
安全対策の観点から知っておくべきポイント
事故を防ぐために、会社(使用者)には以下のような安全配慮義務があります。
・労働安全衛生法第20条により、「事業者は、労働者の安全及び健康を確保するために必要な措置を講じなければならない」と定められています。
・また、プレス機械に関しては、 労働安全衛生規則第131条・134条により、安全囲いや安全装置の設置、定期的な点検・作業主任者の選任・教育が義務づけられています。
・さらに、機械が老朽化していた、安全装置が未作動、教育が十分でなかったという事例が多く、こうした点が「安全配慮義務違反」の判断材料となります。
つまり、事故後だけでなく「なぜ事故が起きたか」「会社にどのような安全義務があったか」「それを果たしていたか」を振り返ることが、労災申請・損害賠償請求において非常に重要です。
労災申請方法
「労災保険」とは・対象になるか?
「労災保険」とは、業務中や通勤中に起きた災害について、治療費・休業補償・障害補償・死亡補償などを行う制度です。
プレス機作業中の事故の場合、通常「業務上の災害(業務災害)」として労災保険の対象になる可能性が高いといえます。
主な給付の種類とポイント
労災保険による給付には以下のような種類があります。利用できる給付が何かをまず確認しましょう。
・療養補償給付:治療費・入院費・通院交通費など、ケガや病気の治療に要する費用。
・休業補償給付:仕事を休まざるを得なかった期間について、給付基礎日額の一定割合が支給される。
・障害(補償)給付:後遺障害が残った場合、等級に応じた給付。
・遺族補償給付・葬祭料:死亡事故の場合、遺族が受けられる給付。
「プレス機事故」のポイント
プレス機事故で特に押さえておきたいポイントを整理します。
・安全装置が機能していたか(光線式センサー、ガード、二重スイッチなど) → 機能しなかった事例が報告されています。
・機械の点検・検査(特定自主検査)の実施有無。プレス機の場合、年間1回の特定自主検査の義務があり、未実施が原因となる事故もあります。
・作業主、作業主任者の選任・教育の実施。プレス機5台以上設置事業場では「プレス機械作業主任者」を選任し付随の教育を行うことが法令で定められています。
・被災者自身の過失がどの程度か。裁判では、作業者側の過失が認められることも多々あります。
これらを整理・記録しておくことで、労災申請・損害賠償請求において重要な証拠となります。
損害賠償請求について
なぜ「労災給付だけ」で済まないのか?
労災保険給付は重要な救済制度ですが、次のような点で「追加的な請求=損害賠償請求」を検討すべき場合があります。
・労災保険では「治療費・休業補償・障害補償」などが支給されますが、たとえば精神的な苦痛(慰謝料)・将来的に失われる収入(逸失利益)・介護費用など、給付の範囲外となる損害があります。
・会社が法令に基づく安全配慮義務を果たしていなかった場合、民法上「債務不履行責任(第415条)」「使用者責任(第715条)」などを根拠に損害賠償責任が認められることがあります。
・特にプレス機事故では、安全装置未設置・点検未実施・教育不足等の会社の過失が明らかになっている事例が多く、損害賠償請求が認められたケースもあります。
請求を検討すべき典型的な項目
以下のような損害について請求を検討していくことになります。
・慰謝料:怪我・切断・後遺障害によって被った精神的苦痛。
・逸失利益:例えば働けなくなった・将来働ける可能性が低くなったために失う収入。
・介護費用・将来の治療・メンテナンス費用。
・家族にかかる負担(家事代行費用など)。
・その他、機械の事故に伴い「生涯にわたる影響」がある場合には、それを見据えた請求が必要になります。
損害賠償請求を行うに当たって押さえるべきポイント
・事故発生状況・機械の仕様・安全装置・点検履歴・教育記録などを可能な限り集める。
・被災者自身の動き・作業内容・過失の有無を整理しておく。過失があっても請求できるケースがあります(後章で詳述)。
・会社との交渉・資料提出・法的手続き(証拠収集や主張立証)を行うための専門的な知識が必要であるため、弁護士を入れることを検討しましょう。
プレス機における労災を弁護士に依頼するメリット
1.手続きの代行・サポート
労災申請や損害賠償請求では、申請書や証拠収集、会社・労働基準監督署・保険機関とのやり取りが必要です。弁護士が入ることで、書類作成や提出、交渉等を代行・サポートできます。
2.会社・保険会社との交渉力を強化
会社が労災申請を渋る・安全体制が疑われる場合、弁護士が入ることで「法的に争う意思あり」と対抗でき、専門知識に裏付けられた,強い交渉を行うことが出来ます。
3.損害賠償請求を有利に進められる
労災保険給付だけではカバーできない慰謝料・逸失利益などを請求するためには、会社側の安全義務違反を立証する必要があります。弁護士による証拠の整理・法的に整理された主張があると、請求が認められる可能性が高まります。
4.過失相殺や会社側の主張に対抗できる
被災者自身に過失があると判断されると、損害賠償額が減らされる「過失相殺」が適用されるケースがあります。
このような場面でも、弁護士が入れば「過失割合」を正しく争ったり、会社側の責任を強く主張したりできます。
5.安心して治療・生活に集中できる
被災直後は身体・心とも大きなダメージを受けています。そのような中で、弁護士に手続きを任せることで、依頼者は治療や回復・生活再建に専念できるという心理的なメリットもあります。
“労災に強い”弁護士とは
プレス機による労災は、機械の仕様・点検履歴・安全装置・教育・作業主任者の選任など「技術的・労働安全衛生的な事情」が絡みます。単に「労災申請できますよ」というだけでなく、機械・安全体制・法令(労働安全衛生法・規則)に詳しい弁護士でないと、現場を正しく把握・主張できない可能性があります。
例えば「安全装置が故障していたが点検がされていなかった」などの事情を捉えて、会社の安全配慮義務違反を立証できるかどうかがポイントです。
依頼を検討すべき状況
以下のような状況の方は、お早めに弁護士への相談を検討してください。
・会社が「労災申請をするのは難しい」「会社負担になる」と言って申請を渋っている。
・後遺障害が残る可能性がある/長期休業が必要になる。
・安全装置の不備・点検未実施・教育が行われていなかった可能性がある。
・被災者自身の過失を会社側・保険会社が主張して減額を図ろうとしている。
・会社側・保険会社の対応が遅い・話が進まない・精神的に疲れている。
こうした状況がある場合には、できるだけお早めにご相談ください。労災の申請・損害賠償請求は「時間が経つほど証拠が散逸する」「身体・生活への影響が増える」という問題もありますので、逃さないうちの対応が重要です。
プレス機における労災にお悩みの方は 弁護士法人晴星法律事務所 へご相談ください
晴星法律事務所では、広島メインオフィス・福山オフィスの2拠点で,製造業・機械設備の労災について豊富な経験を有する弁護士が在籍しており、労災保険給付の申請サポートから、会社側に対する損害賠償請求まで一貫してサポートいたします。
初回相談は無料で承っておりますので,是非お気軽にお問い合わせください。
ご相談の流れ
1.まずはお電話またはLINE・WEBフォームでご連絡ください。事故の概要を簡単にヒアリングします。
2.初回面談時に、作業内容・事故状況・機械仕様・安全体制などを詳細に聴き取り、内容を整理いたします。
3.損害賠償請求の可能性がある場合には、見通し・費用・リスクなどを含めてご説明し、依頼をご検討いただきます。
4.ご契約後は、弁護士が窓口となり、会社や保険会社との交渉を行い、ご依頼者様の安心と利益を守るために尽力します。
最後に
プレス機による労災事故は、ケガそのものだけでなく、その後の生活・家族・仕事に大きな影響を及ぼします。「自分のミスだから…」「会社に迷惑かけたくないから」といった気持ちで、申請・請求をあきらめてしまっては、本来受けられる救済を逃してしまう可能性があります。
もし今、
・プレス機事故に遭われて治療中・休業中である、
・後遺障害の可能性がある、
・会社の対応に不安がある、
という状況であれば、まずは無料でご相談いただければと思います。
労災・損害賠償請求の道のりは、内容によっては複雑で心細いものになりがちですが、あなた一人で抱える必要はありません。私たち“労災に強い弁護士チーム”があなたの声に耳を傾け、ともに最善を目指します。
どうぞお気軽に、弁護士法人晴星法律事務所までご連絡ください。
あなたの安心・生活再建のために、私たちは全力でサポートいたします。