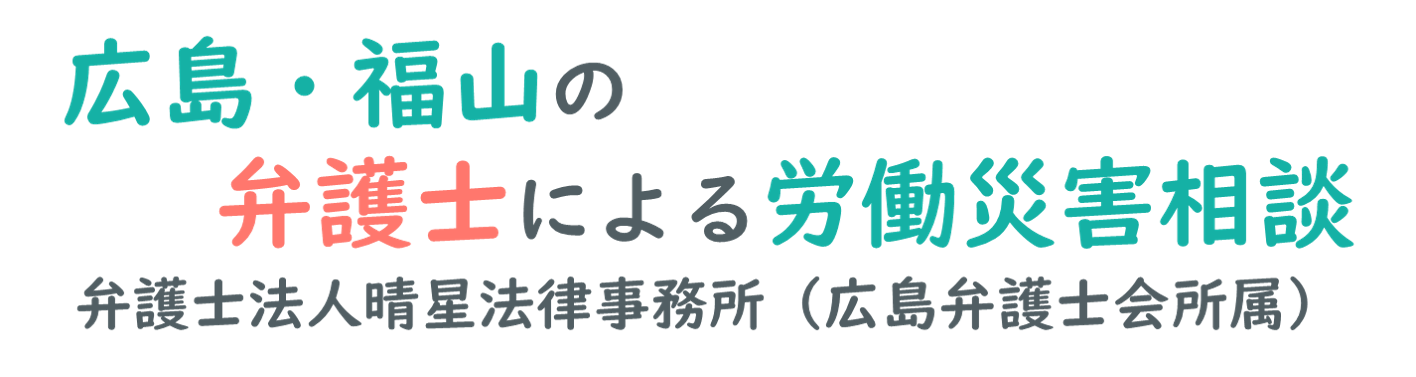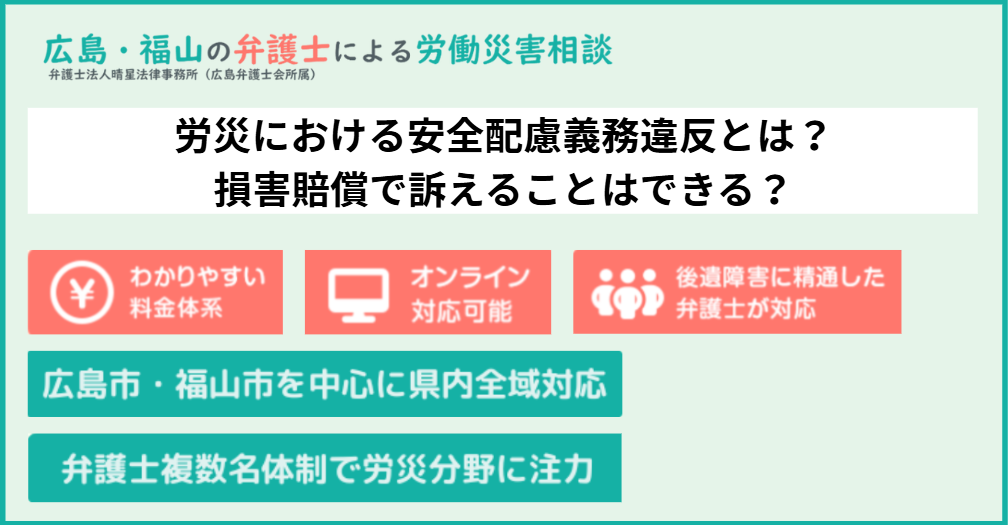
安全配慮義務違反とは
安全配慮義務とは
安全配慮義務とは、会社(使用者)等が、労働者の生命や健康を守るために必要な措置を講じる義務のことをいいます。この義務は 労働契約法第5条にも明記されており、労働者が安全に働くことができる環境を確保するため、会社には労働環境の整備や危険防止措置 を講じる義務があります。
会社がこの義務を怠った結果、労働者が労災事故に遭って負傷したり、過重労働による健康被害を被ったりした場合、安全配慮義務違反となり、会社は被災労働者に対して、損害賠償責任を負います。
安全配慮義務に関する規定
安全配慮義務に関する規定としては、以下のものがあります。
労働契約法第5条:「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」
労働安全衛生法第3条:「事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守だけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。」
また、労働安全衛生法自体が、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする法律であり、同法には、労働災害防止のための多くの規定が定められています。
なお、安全配慮義務は雇用関係にある会社のみならず、直接の雇用関係にない派遣先の会社等に対しても認められることがあります。
安全配慮義務違反になるケースと具体的な事例
過重労働による健康被害(過労死・過労自殺)
長時間労働や極度の業務負担により、労働者が精神疾患や脳・心臓疾患を発症するケースがあります。
・飲食店の従業員が、4か月にわたって毎月80時間を超える時間外労働を行い、急性左心機能不全によって死亡した事例。
会社には、労働者の労働時間を把握し、長時間労働とならないような体制をとり、一時、やむを得ず長時間労働となる期間があったとしても、それが恒常的にならないよう調整するなどし、労働時間、休憩時間及び休日等が適正になるよう注意すべき義務があったにもかかわらず、適切に労働時間が把握されず、長時間労働となっていたのに、会社としてそのような勤務時間とならないよう休憩・休日等を取らせておらず、何ら対策を取っていなかったと判断されました。
労働環境の不備による労災事故
職場の安全対策が不十分なために、労働者が 転落事故や機械による負傷を負うケースも、安全配慮義務違反に該当します。
・スレート葺鉄骨造りのガレージ解体作業中に、誤って鉄骨から足を踏み外し、スレートを踏み抜いて落下した事例。
下請けの会社に対し、被災者との間で、使用従属の関係があったものといえるとしたうえで、同社には、現場に踏み抜きによる墜落防止措置を講ずるべきであったにもかかわらず、同義務に違反し、何ら措置を講じなかったと判断されました。
パワーハラスメントやセクシャルハラスメントの対応の不備
職場におけるパワーハラスメントやセクシャルハラスメントによる被害の対応に不備がある場合も、安全配慮義務違反となることがあります。
・医療法人が運営する病院に勤務中、医療法人の理事長がセクシャルハラスメントを行った事例。
使用者としては、職場におけるセクハラへの対処方針を明確にし、これを周知徹底するべく種々の啓発活動を行うことに加え、個々の申出に対しても適切に対応する義務を負うというべきであり、このような義務に違反してセクハラ行為を招いた場合、行為者自身の責任とは別に、使用者自身も安全配慮義務違反による責任を免れないとしたうえで、セクハラの申出に対する医療法人の対応は、セクハラ防止に関する意識の低さを如実に示すものであって、良好な職場環境を整備、維持すべき法的義務に反するものということができ、医療法人は、原告に対し、安全配慮義務違反があると判断されました。
労災保険だけでは補償されない損害
労災保険の補償範囲
労災事故に遭って怪我を負ったり、疾病に罹患した場合、労災保険から労災保険給付を受給することができます。労災保険には、療養補償給付や休業補償給付、障害補償給付等があり、業務上の災害や疾病による治療費や休業に対する補償、障害に対する補償などが行われます。
労災保険では補償されない損害
これに対し、以下の損害は労災保険では補償を受けることができません。
・精神的苦痛に対する慰謝料
労災保険から、精神的苦痛に対する慰謝料は支給されません。
・逸失利益(将来得られるはずだった収入の損失)の一部
一定以上の後遺障害が残った場合には、障害補償給付を受給することができます。もっとも、障害補償給付は、逸失利益の全てが補償されるわけではありません。
・休業損害の一部
労災事故によって休業し、賃金をもらうことができなくなった場合には、休業補償給付を受給することができます。
しかし、休業補償給付は休業4日目からの支給になります。また、休業補償給付は給付基礎日額の60%×休業日数(休業特別支給金も給付基礎日額の20%×休業日数)しか支給されません。
労災保険では補償されない損害については、 労災事故の発生に責任がある会社に対して請求することになります。
安全配慮義務違反で会社に損害賠償を請求する方法
証拠を集める
安全配慮義務違反を証明するためには、具体的な証拠を確保することが重要です。
具体的な証拠は以下のとおりです。
労働時間の記録(タイムカード、業務メール)
医師の診断書(精神疾患・過労死・労災事故の診断)
職場環境の証拠(写真・動画・証言)
ハラスメントの証拠(録音・メール・LINEのやり取り)
なお、労働基準監督署が労災認定の際に作成した資料は、労働局に対して開示請求をすることができます。
これらの証拠が揃えば、会社の責任を追及しやすくなります。
会社に対する損害賠償請求の方法
会社との交渉
内容証明郵便の送付等により、会社に対して損害賠償を請求します。会社との交渉で解決することができない場合は、裁判所を用いた手続きによることになります。
労働審判の申立て
裁判所を用いた手続きですが、迅速な進行が求められており、3回以内の期日で行われるのが原則です。
労働審判では調停(話し合い)を通じた解決が試みられますが、調停で解決できない場合は審判が行われます。審判に対して異議が申し立てられると民事訴訟に移行します。
民事訴訟の提起
交渉などの話し合いで解決できない場合には、民事訴訟によって解決することになります。
民事訴訟の場合、解決までに1年以上かかることも珍しくありません。
安全配慮義務違反等でお困りの方は、弁護士法人晴星法律事務所までご相談ください
会社に安全配慮義務違反があり、それによって労働災害に遭われた場合、被災された労働者は、労災保険給付の受給だけでなく、会社に対して、労災保険では補償されない損害について損害賠償を請求することができます。
会社に対する損害賠償請求は、証拠の収集や法的な主張等、労災事件に関する専門的な知識も必要となります。
弁護士法人晴星法律事務所では、労災事件に注力した弁護士が全力で対応させていただきますので、会社の安全配慮義務違反をはじめ、労災事故に遭われてお困りの方は、弁護士法人晴星法律事務所までご相談ください。