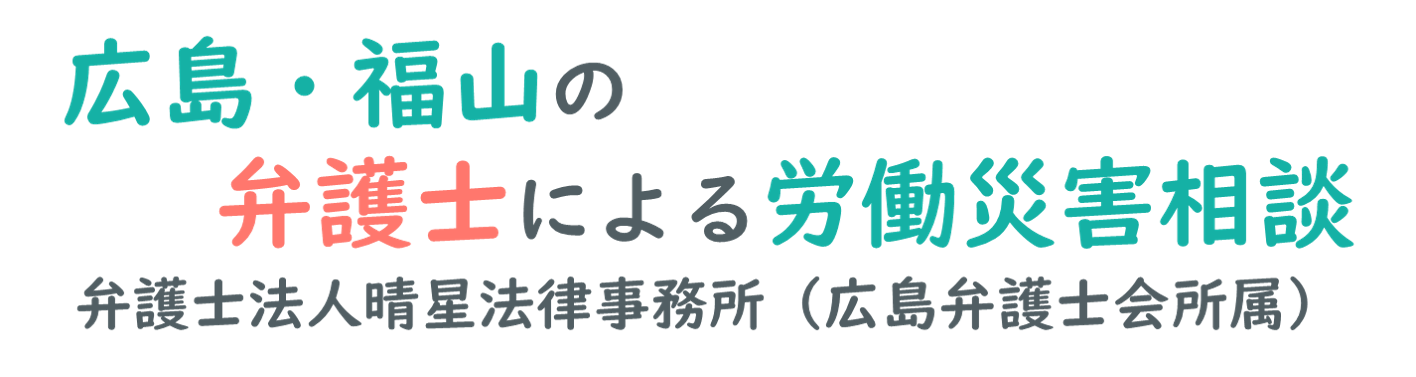近年、工場や研究施設などにおける化学物質による労災事故が増加しています。特に、食料品製造業や化学工業といった業種が多くの割合を占めているといえます。化学物質は、取り扱いを誤ると火傷や中毒、さらには長期的な健康被害をもたらす可能性があります。この記事では、厚生労働省が公表している化学物質による労災事故の発生事例を解説し、重篤な後遺障害が残った場合の補償や、症状固定までの対応について説明します。
化学物質による労災事故の発生事例と補償のポイント
厚生労働省のサイトには、さまざまな化学物質による労災事故の事例が掲載されています。その中から代表的なものをいくつか取り上げ、事故の原因や発生状況を詳しく見ていきます。
事例① 塗膜剥離剤の吹付け作業に従事していた作業員が意識を失う
事故概要
高架橋塗装工事のつり足場内で塗膜剥離剤の吹付け作業作業を行っていた作業員が、意識を失い、病院に搬送されました。現場は、剥離剤等の飛散防止のため養生され、養生により気流が発生しない環境となり、剥離剤から揮発したベンジンアルコールが高濃度で作業場に満たされ、防毒マスクの吸収缶の許容量を超えた疑いや、剥離剤をエアレススプレーガンにより噴霧したため、防護服の性能を超える量のベンジルアルコールが、防護服を透過し、経皮により暴露した疑いがあるとされた事例。
原因と問題点
・作業場所の換気が不十分であった。
・作業環境管理が不十分であった。
・換気、排気装置が設置されていなかった。
・適切な保護具が使用されていなかった。
ことなどが考えられています。
事例② 清掃業に従事していた被災者が救急搬送される
事故概要
被災者は、ピットと沈殿槽をつなぐ配管のつまりを確認する際、防毒マスクを着用していませんでした。被災者が沈殿槽の近くを歩いていた際、意識がもうろうとし、緊急搬送され、急性ガス中毒と診断されました。
原因と問題点
・作業標準書の不備があった。
・防毒マスクを着用していなかった。
・安全衛生教育が不十分であった。
・危険有害性の認識不足があった。
ことなどが考えられています。
補償のポイント
労働者が業務を原因として負傷したり、疾病に罹患したときは、労災保険の対象となります。このことは、化学物質による負傷や疾病の場合も同様です。そのため、化学物質による労災事故に遭われたときは、まずは労災申請をすることが重要です。労災申請は、勤務先の会社が協力して申請をしてくれることもありますが、会社が協力してくれない場合には、被災者自身で労働基準監督署に労災申請をすることもできます。
労災が認定されると、次のような労災保険給付を受けることができます。
療養補償給付
労災病院等の指定医療機関等で、無料で治療や薬剤の支給などを受けることができます(療養の給付)。指定医療機関等以外の医療機関や薬局等で療養を受けたときには、その療養にかかった費用の支給を受けることもできます(療養の費用の給付)。これらの給付は、傷病が治ゆ(症状固定)するまで行われます。
休業補償給付
労災による負傷や疾病による療養のために労働することができず、賃金を受けられない場合は、4日目から休業補償給付を受けることができます。給付額は、給付基礎日額の60%です。これに加えて、休業特別支給金として給付基礎日額の20%の支給も受けることができます。
症状固定後に一定以上の後遺障害が残る場合には、労災保険の障害補償給付の対象となります。重篤な後遺障害が残ることもあるため、症状固定後に適切な後遺障害等級認定を受けることが重要です。
また、労災事故の被災者がお亡くなりになってしまった場合には、被災者のご遺族は、遺族補償給付を受けることができます。
化学物質による労災で後遺障害が残る場合
化学物質による労災では、次のような後遺障害が残る可能性があります。
・呼吸器系の障害(有機溶剤や粉塵などを長期間吸い込むことによる肺機能の低下)
・視力の低下(化学薬品などが目に入ることで角膜損傷などを引き起こす)
・皮膚の変形(重度の化学熱傷などによる皮膚移植や瘢痕)
労災保険の障害補償給付は、認定された後遺障害等級によって異なります。後遺障害が残る場合は、適切な補償を受けるためにも、労災保険の後遺障害等級認定を受けることが重要です。
化学物質による労災と精神疾患の関連性
化学物質による労災は、肉体的な障害だけでなく精神疾患を引き起こすリスクもあります。
そして、精神疾患に罹患した場合も、労災保険の対象になる可能性があります。ただし、精神疾患の場合も症状固定まで治療を継続することが重要です。十分な治療を受けた上で、必要に応じて障害補償給付の請求を検討してください。
会社に対する損害賠償請求について
労災が認定されると、労災保険給付を受けることができますが、慰謝料は労災保険から支給を受けることができません。また、後遺障害が残った場合の逸失利益についても、労災保険から十分な補償が受けられるとは限りません。労災保険から補償を受けられないこれらの損害は、労災事故の発生に責任がある会社に対して請求することになります。特に、後遺障害が残ったような場合は、傷害慰謝料(入通院慰謝料)だけでなく、後遺障害慰謝料や逸失利益が高額になることもあります。例えば、東京地裁平成30年7月2日判決では、被災者が化学物質過敏症等に罹患したことについて会社に対して損害賠償を請求した事案において、2000万円近くの損害賠償が認められています。一方、数日の治療期間で完治し、後遺障害も残らなかったような場合には、会社に請求できる損害賠償額は低くなる傾向にあります。
そのため、特に、後遺障害が残るような場合には、労災事故の発生に責任がある会社に対して損害賠償を請求することを検討するべきといえます。
相談を検討するタイミング
化学物質による労災事故は、正しい知識と対策があれば防ぐことが可能ですが、万が一事故が発生した場合には、速やかに適切な補償を受けることが重要です。
特に、後遺障害が残るような場合には、適正な補償を受けるためにも弁護士へ相談することをおすすめします。
例えば
・呼吸器や視力の障害が残った場合
・重度の化学熱傷で皮膚移植などの治療が必要になった場合
などです。
また、精神疾患にも罹患した場合は、症状固定後に障害補償給付の申請を検討するのがよいでしょう。
なお、じん肺症やアスベスト肺(石綿肺)等に罹患した場合は、症状固定することが基本的にはなく、症状固定前に会社に対して損害賠償請求をすることがあります。 弁護士法人晴星法律事務所では、障害補償給付申請時のサポートや会社に対する損害賠償請求などについて、労災事件に注力した弁護士が対応いたします。また、精神疾患にも罹患された場合など、症状固定後のご相談もお受けしておりますので、そのような場合は、まずは治療に専念していただければと思います。化学物質による労災事故をはじめ、労災事故に遭われてお困りの方におかれましては、是非、ご相談いただければと思います。