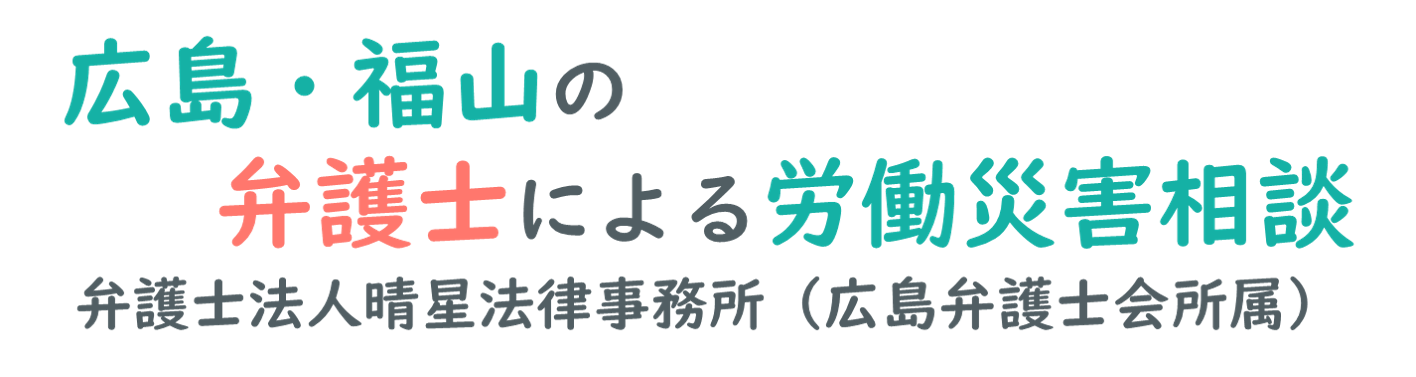労災問題に関するお問い合わせを多くいただいておりますが、中でも精神疾患、特にパワーハラスメント(パワハラ)によるうつ病に関するご相談が増加しています。
精神疾患は労災認定が難しいケースも多く、治療に長期間を要することも珍しいことではありません。
また、会社に対する損害賠償請求においては、症状固定後の対応が重要となります。
本記事では、精神疾患の労災申請を検討されている方に向けて、症状固定の概念や、精神疾患における治療から会社に対する損害賠償請求の流れなどについて解説します。
症状固定とは?
まず、症状固定についてご説明します。
症状固定とは、業務上の負傷又は疾病に対して、医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待し得ない状態を指します。
会社の業務によって精神疾患に罹患した場合、まずは、その治療をすることが重要です。
パワハラが原因でうつ病等の精神疾患に罹患した場合も、会社の業務に起因して精神疾患に罹患したということなので、労災申請をすることができます。
労災が認定されれば、労災保険給付を受けることができ、治療に必要な費用も労災保険から給付を受けることができます。
そして、治療によって元の状態に回復すれば一番よいのですが、治療を続けても労災事故に遭う前の状態に戻らないケースもあります。
このような、治療を続けてもそれ以上回復しない状態が症状固定なのです。症状固定は、会社に対する損害賠償請求においても、重要なポイントとなります。
なお、治療に必要な費用などは労災保険から給付を受けることができますが、労災保険から慰謝料は支給されません。
また、後遺障害が残ったことによる逸失利益も、労災保険から十分に補償を受けられるわけではありません。
労災保険によっては補償されない慰謝料等の損害は、労災事故の発生に責任がある会社に対して請求する必要があります。
症状固定が重要な理由
症状固定が重要な理由は以下のとおりです。
後遺障害の認定が可能となる
症状固定後に、治療によっても改善しない一定以上の症状が残った場合、後遺障害の等級認定を受けることができます。
後遺障害等級が認定されると、認定された等級に応じて、労災保険から障害補償給付を受けることができます。
また、基本的には、後遺障害等級が認定されなかったときに比べて、会社に請求できる損害賠償額も高額になります。
請求額の算定が可能になる
症状固定前でも、損害賠償請求をすることができないわけではありません。
しかし、症状固定前は、治療が続いているため、将来必要となる治療費や後遺障害の有無・程度が明らかではありません。
ですが、症状固定後であれば、症状固定時までの治療費や後遺障害の有無・程度も明らかになっているため、損害賠償額の計算が可能になります。
紛争の解決がスムーズになる
症状固定前の場合、損害賠償を請求された会社からしても、妥当な金額を算定することが困難なため、会社との交渉もうまく進みません。
一方、症状固定後の状態を基にした請求であれば、妥当な金額をある程度は算定することができるため、症状固定前に比べて、会社との交渉をスムーズに進めることができるでしょう。
精神疾患における症状固定について
次に、精神疾患における治療や症状固定について具体的に解説します。
精神疾患の治療内容と特性
精神疾患、特にパワハラによるうつ病の場合、以下のような治療を経ることが一般的です。
薬物療法
抗うつ薬や抗不安薬などの薬物が処方され、症状の軽減を目指します。
カウンセリング・心理療法
心理療法士やカウンセラーとの対話を通じて、ストレスの軽減や心理的負担の解消を図ります。
生活リズムの改善
規則的な生活習慣の確立や、休職期間中の生活指導が行われます。
職場環境の改善
職場復帰に向けて、適切な環境が整えられることも治療の一環として重要です。
症状固定までの時間がかかる理由
精神疾患において症状固定が長引く理由には、以下のような要因があります。
治療の効果が現れるまでに時間がかかる
精神疾患は薬物や心理療法の効果が現れるまでに数週間から数ヶ月を要することが一般的です。
症状の波がある
精神疾患の症状は一進一退であり、短期間で症状固定の判断を下すことが難しい場合があります。
症状固定後の損害賠償請求の重要性
精神疾患では、症状固定後に残る症状が後遺障害として認定されることで、適切な損害賠償額の請求が可能となります。
後遺障害等級が認定される
損害の内容は、傷害部分と後遺障害部分の2つに分けられます。
傷害部分は、治療費や傷害慰謝料(入通院慰謝料)などの損害であり、後遺障害部分は、後遺障害慰謝料や逸失利益といった損害です。
このうち、後遺障害部分は、症状固定後に残存した後遺障害の程度によってその額も異なります。
そして、後遺障害の程度は、症状固定後に認定された後遺障害等級が一つの目安となります。
症状固定前の請求は不十分な結果になりやすい
症状固定前は、後遺障害等級の認定がされていないため、後遺障害部分の算定が困難になります。
また、傷害部分についても、例えば、治療費や傷害慰謝料(入通院慰謝料)は、症状固定までに要した治療費や期間などに基づいて算定するため、症状固定前にはこれらの金額を正確に算定することは困難です。
そのため、治療が途中の場合、請求額の算定が不確実となり、十分な補償を得られない可能性があります。
適切なタイミングでのご相談を
精神疾患の労災事故における会社に対する損害賠償請求は、症状固定後に行うことが適切です。以下のポイントを踏まえ、準備を整えてからお問い合わせいただければ、スムーズに手続きを進めることができます。
・現在治療中の方は、まず治療に専念してください。
・主治医と相談の上、症状固定のタイミングを確認してください。
・症状固定後に後遺障害等級の認定を受ける準備を進めてください。
弁護士法人晴星法律事務所におけるサポート体制について
業務が原因で精神疾患に罹患した場合、怪我をした場合とは異なり、会社から労災事故ではないと言われることもあります。
しかし、労災事故に該当するかどうかを決めるのは会社ではありません。
被災者としては、労災申請に協力してもらえるよう、会社に求めるべきです。
もし、会社が労災申請に協力してくれない場合には、被災者自身で労働基準監督署に労災申請をすることができます。
また、精神疾患に関する労災事件においては、治療期間が長引きやすく、症状固定までに長期間を要することも多くあります。
労災が認定されましたら、療養補償給付等の労災保険給付を受けながら、症状固定までは治療に専念しましょう。
精神疾患によって働くことができず、収入を得られなくなった場合は、4日目から、休業補償給付を受けることもできます。
弁護士法人晴星法律事務所では、症状固定後のご相談からでも受け付けておりますので、まずは治療に専念していただければと思います。
また、当事務所では、労働者災害補償保険診断書(いわゆる後遺障害診断書)作成の際の診察の同席や、診断書の確認等をはじめとした後遺障害申請のサポート、会社に対する損害賠償請求などについて、労災問題に注力した弁護士が全力で対応いたします。
業務によって精神疾患に罹患された方におかれましては、治療が終わられて症状固定した後で構いませんので、一度当事務所までご相談いただければと思います。