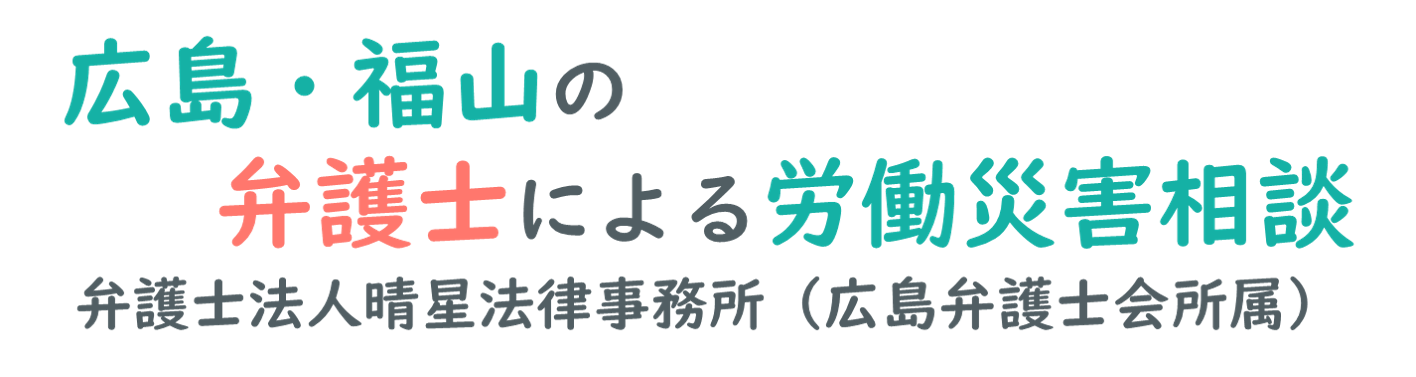厚生労働省の「令和5年労働災害発生状況の分析」によると、平成30年から令和5年までの間、製造業における死傷災害人数は、食品製造業が最も多くなっています。
また、死病災害人数も、他の製造業に比べて、食品製造業が多い傾向にあります。
そして、食品製造業は、以下のように事故の態様も様々であり、多様な危険が内在しているといえます。
・ベルトコンベヤーを洗浄作業後、付着部を取り除こうとして手首が巻き込まれた。
・ロール機のローラーを回転させてタオルで拭いていたところ、タオルが巻き込まれて、そこから手指も巻き込まれた。
・水洗い作業中、ホースが回転部に巻き込まれ、取り出そうとしたところ、回転部に腕を巻き込まれた。
・攪拌機で攪拌作業中に、攪拌羽に巻き込まれた。
・材料等を包丁で切っていたところ、指を切った。
・スライサーで材料の切り落とし作業中に刃に接触して指を切った。
・麺の切断用カッター付製麺機の清掃作業中にカッターが作動したため、指を切断した。
・床の水濡れや油汚れに足を滑らせて転倒した。
・凍結している路面に足を滑らせて転倒した。
・高濃度の消毒剤に手が触れて、皮膚を負傷した。
・材料の運搬中、廊下の傾斜部で無理に力を入れた際、足を負傷した
・在庫確認作業中、バランスを崩して脚立から落下した。
仕事中にこのような事故に遭ってしまうと、今後の治療費や収入への不安が大きいと思います。
そこで、今回は、食品製造業で労災事故に遭ってしまったときの対応について解説します。
仕事中の怪我は労災申請をするべき
労働者が業務を原因として負傷してしまった場合、労災保険給付を受けることができ、そのためには労災申請をする必要があります。
労災申請は、会社が被災労働者の代わりに行ってくれることも多いです。
一方で、仕事中に怪我をしたにもかかわらず、会社から「労災申請はするな」「治療費は会社が支払うから労災にはしないでほしい」「今回の事故は労災事故ではない」などと言われ、労災申請に会社が協力してくれないこともあります。
しかし、労災に該当するかどうかは会社が決めることではありません。
会社が労災申請に協力してくれないときは、被災労働者自身で労災申請をすることもできます。
労災が認定されると、治療に必要な療養補償給付や、怪我で働けないときの収入の補償となる休業補償給付、後遺障害が残ってしまったときには障害補償給付といった労災保険給付を受けることができ、怪我の治療費や収入等に対する負担が軽減されます。
食品製造業の場合は、滑って転倒して骨折をしたり、刃物で指などを切ったりしてしまう等、治療が長期間に亘ることや、後遺障害が残ってしまうことも珍しくありません。
会社が長期間に亘る治療費を全て支払ってくれるとは限りませんし、後遺障害が残って失われてしまった労働能力に対する補償を会社が自発的にしてくれることはほとんどないと言っていいでしょう。
労災申請をしないと、本来受けられたはずの補償を受けることができなくなってしまいますので、仕事中に怪我をしたときは、労災申請をするべきです。
後遺障害が残る大きな怪我になることも
労災認定がされると、療養補償給付や休業補償給付等を受給しながら治療をすることができますが、治療を継続したにもかかわらず後遺障害が残ってしまうこともあります。
そして、治療を続けたにもかかわらず、一定の後遺障害が残ってしまったときは、障害補償給付を受給することができます。
障害補償給付の対象となる後遺障害は、第1級から第14級までの等級が定められています。
例えば、片手の中指を切断して失った場合には第11級、片方の下肢に偽関節が残り、著しい運動障害が残ってしまった場合には第7級といったように、等級認定の基準が定められています。
また、認定される等級により、受給することができる障害補償給付の支給額も異なります。
労災申請(認定)の流れ
労災申請は、基本的には所轄の労働基準監督署に所定の請求書を提出することにより行います。
前述のように、労災事故が発生した場合、会社が被災労働者に代わって労働基準監督署に所定の請求書を提出してくれることも多いですが、会社が労災申請に協力してくれないときには、被災労働者自身で労働基準監督署に所定の請求書を提出することもできます。
障害補償給付の請求には、労働者災害補償保険診断書(いわゆる後遺障害診断書)の提出も必要となります。
労働者災害補償保険診断書は医師に作成してもらうことになりますが、障害補償給付の認定には、労働者災害補償保険診断書の記載内容が非常に重要です。
記載内容に過不足がないか、提出前にしっかりと確認するようにしましょう。
また、障害補償給付の請求時には、労働基準監督署の担当者等との面談が行われることもあります。この面談でも、残っている症状について、きちんと伝えることが重要です。
労災が認定されると、労災保険給付を受けることができます。
しかし、労災が認定されず、不支給決定通知が届くこともあります。労災が認定されなかった場合は、審査請求等により、不服申立てをすることが可能です。
労災保険では十分な補償を受け取ることができない
労災が認定された場合でも、労災保険から慰謝料等は支給されません。
また、休業補償給付や障害補償給付も、休業や後遺障害によって生じた損害の全てが補償されるわけではありません。
これらの労災保険から補償を受けることができない損害については、労災の発生に責任がある会社に対して請求することになります。
会社に対して損害賠償請求をするという選択肢
使用者である会社には、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする義務(安全配慮義務)があります(労働契約法5条)。
また、使用者である会社には、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任(使用者責任)もあります(民法715条)。
このような義務に違反して労災事故が発生した場合、労災保険から補償を受けることができない損害の賠償は、会社に対して請求することになります。
もっとも、労災事故の発生に会社の義務違反があったのかどうかを判断することは容易ではありません。
また、会社に対して損害賠償を請求すると、会社から安全配慮義務等の義務違反はなかったとか、被災労働者の不注意で発生した事故であるため、会社に責任はないといった主張をされることも多くあります。
このような会社の主張に対しては、法的な根拠に基づいた反論をすることが重要となります。
まずは下川法律事務所へご相談ください
食品製造業においては、労災事故の態様も様々です。また、労災事故によって怪我を負う部位も上肢、下肢、体幹、頭部等多岐に渡り、中には、後遺障害が残る大怪我になることもあります。
そして、労災事故に遭われたときには、後遺障害等級が認定されるかどうかや会社に対して安全配慮義務違反等の責任が認められるかどうかが、被災労働者に対する補償という観点から重要となります。
もっとも、労災申請や会社に対する損害賠償請求について、具体的にどのように進めればいいのかよく分からないと思われる方もおられるかと思います。
また、ご自身で会社に対して損害賠償請求をすることに不安を抱かれる方も多いと思います。
弊所にご相談いただけましたら、労災申請の流れや後遺障害の認定について、個別の事案に沿った具体的なアドバイスをさせていただきます。
また、ご依頼いただけましたら、障害補償給付の請求において必要となる労働者災害補償保険診断書の記載内容の確認や労働基準監督署の担当者等との面談の同席、会社に対する損害賠償請求も代わりに行うこともできます。
食品製造業をはじめ、仕事中の事故が原因で負傷された方におかれましては、是非、下川法律事務所にご相談いただければと思います。