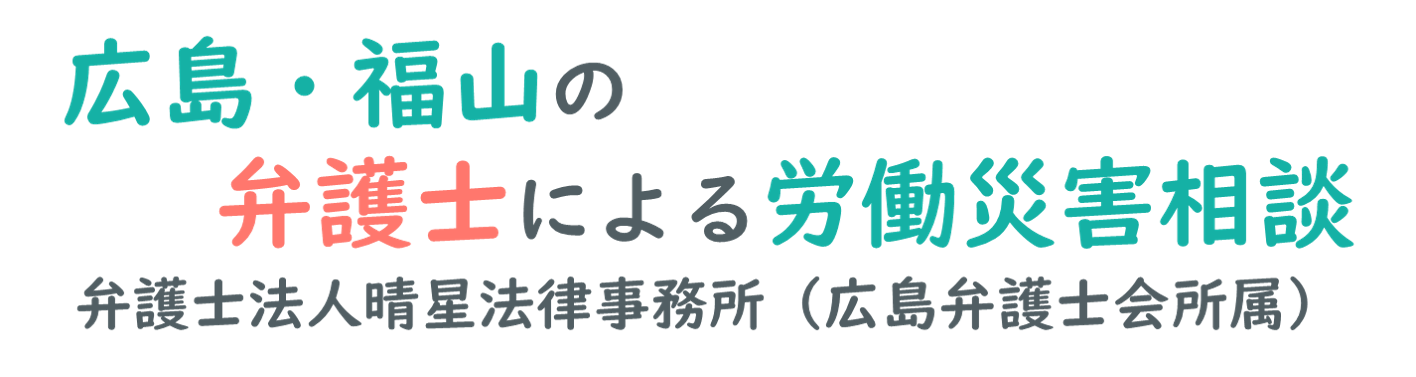目次
はじめに
夏になると毎年のようにニュースで報道される「熱中症」。炎天下での作業がある建設現場や運送業、工場内作業、また最近ではオフィスでも空調不良により熱中症にかかる方が増えています。そのような中、
「仕事中に熱中症になった場合、労災保険は使えるのか?」
というご相談も多く受けます。
今回は、熱中症と労災の関係について、わかりやすく解説し、会社側の責任や弁護士に相談すべきタイミングについてもお伝えします。
職場における熱中症の発生数
年々増える職場での熱中症
厚生労働省の発表によると、職場での熱中症による死亡者及び休業4日以上の業務上疾病者の数は、2024年には1,195人、うち30人が死亡しています。2020年以降では、特に建設業、製造業、運送業、警備業など外気温や機械熱の影響を受けやすい現場での被害が目立ちます。特に、2024年の死亡災害については、建設業において8件と最も多く発生しています。
熱中症の重症度は?
熱中症は以下のように重症度で分類されます。
【Ⅰ型(軽症)】めまい、大量の発汗、立ちくらみ、生あくびなど
Ⅰ型(軽症)の場合は、冷所での安静、体表冷却、水分とナトリウムの補給など、通常は現場で対応することが可能です。
【Ⅱ型(中等症)】頭痛、吐き気、倦怠感、虚脱感、集中力や判断力の低下
Ⅱ型(中等症)の場合は、医療機関での診療が必要とされています。
【Ⅲ型(重症)】意識障害、けいれん、小脳症状等
Ⅲ型(重症)の場合は、入院加療(場合により集中治療)が必要とされています。
熱中症は、たとえ軽症の場合でも、そのまま仕事を続けることで命の危険を伴う状態に陥るケースもあるため、早期の対応が必要です。
熱中症は労災として認められる?
労災保険とは?
労災保険とは、労働者が「業務上の災害」によりケガや病気になったときに、療養補償給付や休業補償給付などが支給される制度です。労災保険給付の申請は労働基準監督署に対して行います。業務中や通勤途中の事故・疾病が対象になります。
熱中症も労災の対象となるか?
労働基準法施行規則別表第1の2第2号8において「暑熱な場所における業務による熱中症」が業務上の疾病として規定されており、仕事中や通勤途中に熱中症になった場合も、労災認定の対象となることがあります。ポイントは、その熱中症が業務に関連しているかどうかということになります。
労災の認定基準
労働基準監督署による判断
公益財団法人労災保険情報センターによると、熱中症の認定要件は、概ね次のとおりとされています。
【一般的認定要件】
・業務上の突発的又はその発生状態を時間的、場所的に明確にし得る原因が存在すること。
・当該原因の性質、強度、これが身体に作用した部位、災害発生後発病までの時間的間隔等から災害と疾病との間に因果関係が認められること。
・業務に起因しない他の原因により発病(又は憎悪)したものでないこと。
【医学的診断要件】
・作業条件及び温湿度条件等の把握
・ 一般症状の視診(けいれん、意識障害等)及び体温の測定
・ 作業中に発生した頭蓋内出血、脳貧血、てんかん等による意識障害等との鑑別診断
また、夏季における屋外労働者の日射病が業務上疾病に該当するか否かについて、
「作業環境、労働時間、作業内容、本人の身体の状況及び被服の状況その他作業場の
温湿度等の総合的判断により決定されるべきものである。」とされおり(昭26.11.17基災収第3196号)、熱中症が労災に該当するかどうかは、最終的には労働基準監督署が判断します。
熱中症が労災として認められた事例
事例1:警備業務に従事していた80代の被災者が発症した事例。
80代の警備員が屋外の工事現場で警備業務に従事していた。休憩後、現場に戻った際にふらついて倒れました。意識があり、1時間休憩後、タクシーで病院へ行き、その後病院で死亡しました。
事例2:屋外で作業を行っていた被災者が発症した事例。
製造業に従事していた30代の被災者が、午前中から直射日光の下で機械修理を行っていたところ、正午過ぎ頃までに体調不良となり、事務所で休憩していたが、症状が回復せず、夕方、救急車で病院に搬送されたものの、熱中症が原因で死亡しました。
事例3:農場の見回りを行っていた50代の被災者が発症した事例。
農場の見回りを行った被災者が、農場近くの路上で、社用車の中でぐったりしているところを発見され、その場で死亡が確認されました。屋外作業を行っていたことなどから、死因は熱中症とされたようです。
職場において熱中症になった場合に会社の責任はある?
安全配慮義務とは?
労働契約法第5条に基づき、使用者(会社)は「労働者がその生命・身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする義務」があります。これを「安全配慮義務」といいます。そして、この安全配慮義務に違反して被災者が熱中症になった場合には、使用者(会社)に対して損害賠償を請求することができます。
職場における熱中症対策の強化について
熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日より、以下の措置が事業者に義務付けられるようになりました。
1.熱中症を生ずるおそれのある作業(WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの)を行う際に、①「熱中症の自覚症状がある作業者」②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
2.熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、①事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等②作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせることなど、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること。
会社に責任がある場合
令和7年6月1日から上記の措置が事業者に義務付けられたため、当該義務に違反して熱中症になった場合には、会社が労働者に対して損害賠償責任を負う可能性が高くなります。また、十分な休憩時間や水分補給の指導がなかった、空調設備や日除けが設置されていなかった、炎天下で過重労働が強いられていたといったような場合にも、会社に責任が認められる可能性があります。
労災と会社の責任は別物
労災保険は、たとえ会社側に落ち度が認められない場合であっても、業務に起因して負傷したり疾病にかかった場合には、一定の給付を受けることができる制度です。
具体的には、医療費に相当する療養補償給付や、休業中の収入を補償する休業補償給付などが支給対象となります。
もっとも、労災保険からは、慰謝料や逸失利益の一部等については支給されません。
これに対し、会社に対しては、労災保険から支給されない慰謝料や逸失利益の一部等の損害賠償も請求することができます。ただし、会社に対してこれらの損害賠償を請求することができるのは、会社に安全配慮義務違反等の責任が認められる場合に限られます。
弁護士に相談や依頼をすべき理由
労災の流れについてアドバイスを受けることができる
ご自身で労災の申請を行った場合であっても、労災認定に至るまでの手続の流れや、認定後の対応について不明な点が生じることは少なくありません。弁護士に相談することで、労災認定に至るまでの具体的な手続の流れや、認定後に必要となる対応について、専門的な視点から丁寧な説明を受けることが可能となります。
損害賠償請求の交渉も対応
会社に安全配慮義務違反をはじめとする責任がある場合、弁護士が代理人として会社側と交渉を行い、慰謝料等損害賠償の請求を行うことができます。弁護士が入ることで交渉が円滑に進み、適正な補償を得られる可能性が高まります。
退職後やパート・アルバイトでも対象
労災は正社員だけでなく、パートやアルバイトでも対象です。また、退職後であっても当時の業務が原因であれば、会社に対して損害賠償を請求することができる可能があります。このような事項に関する判断も含め、専門家のアドバイスを受けることができます。
熱中症による労災事故についてお悩みの方は弁護士法人晴星法律事務所へご相談ください
仕事中に熱中症に罹患された場合には、まずは無理をせず、速やかに医療機関を受診されることが重要です。
そのうえで、「この熱中症は労災にあたるのか」「会社に対して責任を問うことができるのか」といった疑問をお持ちの方は、労災問題に注力している弁護士へのご相談をお勧めいたします。
熱中症も、業務との因果関係が認められる場合には、労災として認定される可能性があります。また、会社に対する損害賠償請求を検討する際には、法的な知識や経験が求められる場面も多くあります。
当事務所では、労災に関する豊富な相談実績があり、熱中症をはじめとする職場での事故に関するご相談を多数取り扱っております。「もしかすると労災かもしれない」とお感じになられた方は、初回相談は無料ですので、お一人で悩まず、弁護士法人晴星法律事務所までお気軽にご相談ください。